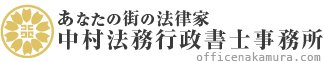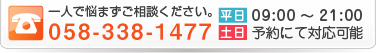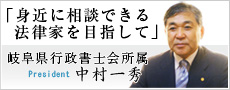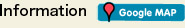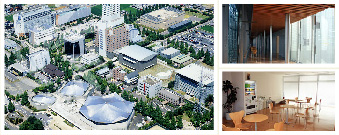HOME > 相続・遺言・家系図 > 相続・遺言書の流れ
- 相続・遺言・家系図
- 相続・遺言書について
- 相続・遺言書の流れ
- 家系図
- 相続・遺言書の良くあるご質問
業務対応地域

お気軽にお問い合わせください。
岐阜県
(大垣市・岐阜市・羽島市・各務原市・瑞穂市・本巣市・多治見市・美濃市・美濃加茂市・可児市 土岐市・海津市・関市・安八町・神戸町・養老町・池田町・大野町・関ヶ原町・笠松町・岐南町など)
愛知県
(名古屋市・北名古屋市・一宮市・稲沢市・愛西市・岩倉市・江南市・清須市・小牧市・犬山市 春日井市・津島市・弥富市・春日町・七宝町・美和町など)
三重県
(津市・桑名市・いなべ市・四日市市・鈴鹿市・亀山市など)
相続・遺言・家系図
相続・遺言書の良くあるご質問
相続ってどういう事ですか?
相続とは、お亡くなりになった(被相続人という)方が生前に持っていた財産の全て(相続財産という)を、相続する権利がある人(相続人という)が譲り受けることです。
相続はいつから始まりますか?
相続は、被相続人の死亡によって開始します。
葬儀までの流れの流れを教えてください?
下記の流れになります

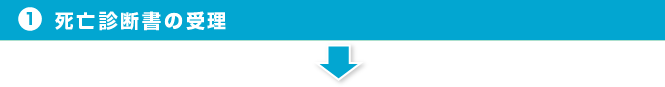
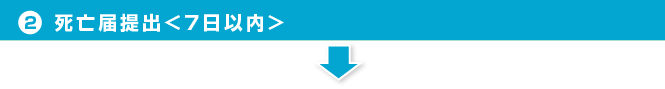
![]()
死亡届の提出方法を教えてください?
先ずは死亡診断書を受け取ります
まず病院から死亡診断書をうけとります。A3の用紙です。その用紙の右半分が死亡診断書で担当医のサインがあります。用紙の左半分が死亡届けの書類になっています。
この用紙は1枚しかありませんので紛失しないようにしてください。
※病院以外に亡くなった場合はかかりつけの医師に、かかりつけの医師がいない場合は病院に遺体を運び、そこの医師に書いてもらいます。
提出する場所
死亡した場所あるいは、死亡した人の本籍地、または死亡した人の住所の市町村役場の戸籍課になります。
提出する期限
死亡を知った日から7日以内ですが、死亡届が提出されていないと遺体を火葬できず葬儀が遅くなってしまいますので、できる限り早く出すことになります。
死亡届を提出する義務のある人
民法は次の順序で、届出義務のある人を定めています。
- (1)同居親族
- (2)親族以外の同居者
- (3)家主、地主、土地・家屋の管理人
- (4)同居していない親族
遺体を火葬するためには、死亡届を出すとともに市町村役場に備え付けてある死体火葬許可申請書に必要事項を記載して、申請します。
その後、市町村役場から交付された死体火葬許可申請書を火葬場に持参すると火葬してもらえます。
しかしこれで終わりではなく納骨という手続をしなくてはいけません。
火葬場の管理事務所は死体火葬許可申請書に裏書して返してくれます。
裏書された死体火葬許可申請書は、火葬証明書&埋葬許可書になり、納骨する際に墓地の管理者に提出しなくてはいけません。
以上ここまでが、死亡届の提出から納骨までの手続きです。
亡くなられた方の親族は精神的なショックや葬儀の手配などさまざまな準備などで見も心も大変かと思われます。身近な友人や、葬儀社の方などの力を借りることも遠慮なくなされることを、お勧めします。
夫婦・長男・長女の家族で夫が亡くなりました。相続人は誰になりますか?
下記のとおりです。

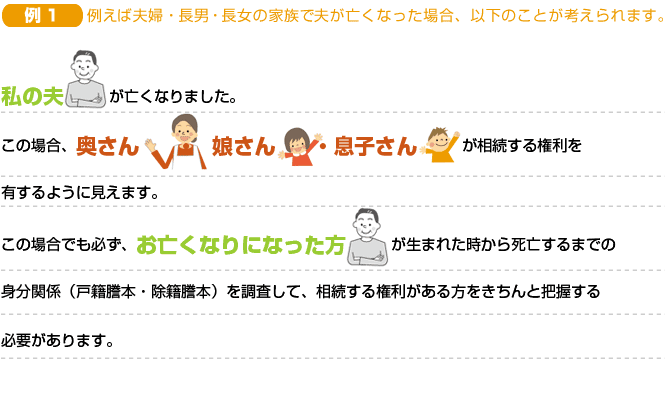
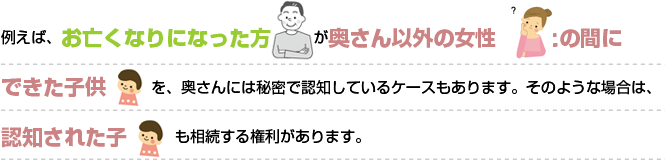
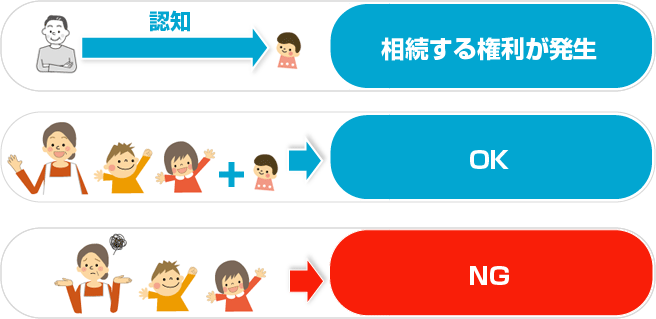
相続の問題は、「誰が」「何を」相続するのかにつきます。
相続についての話し合いは、相続する権利がある方全員で行わなければなりません。相続する権利がある方全員が参加しない話し合いで決まったとしても、その効力は認められません。
そのため、誰が相続人であるかを確認する必要があります。遺言書に指示があった場合はそれに従い、指示がない部分や遺言がなかった場合は、法定相続分に基づき確定します。
ここで大切なのは、相続人は明確と思われる場合でも、必ず被相続人の戸籍謄本、除籍謄本を取って、出生から死亡まですべて調べます。第3順位の兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人の親までさかのぼってください。あとで思わぬところから相続人が出てくることがあります。分割協議の前だったら相続人として協議に参加することになりますし、分割協議後ならば価額で支払うことになります。
相続人ってどこまでですか?
相続人=配偶者相続人+血族相続人
お亡くなりになった方の配偶者は、常に相続人となります。配偶者以外の方は、次の順序で配偶者と共に相続人になります。
| 第1順位 | 子供 相続よりも前に子供が死亡している場合、お亡くなりになった方に孫がいれば、孫が子供に代って相続人になります。 |
|---|---|
| 第2順位 | 父母 相続よりも前に父母が死亡している場合、祖父母が相続人になります。 |
| 第3順位 | 兄弟姉妹 相続よりも前に兄弟姉妹が死亡している場合、甥っ子・姪っ子が相続人になります。 |